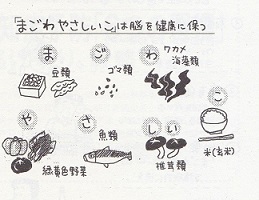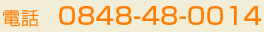���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��
��搶�i���@���j�̃u���O
��������� | |||||||||||
| |||||||||||
���߂Ă̍��ғ^���L | |||||||||||
| |||||||||||
�J���X�ɂ��H�Q | |||||||||||
| |||||||||||
�s�o�ɂ����ɂɏP���� | |||||||||||
| |||||||||||
�����F���Ȍ��f�ɂ��� | |||||||||||
| |||||||||||
�ʂ˂����n | |||||||||||
| |||||||||||
�X�C�X���{�ҁu���Ԗh�q�v��ǂ�� | |||||||||||
| |||||||||||
�u�t�H���X�g�A�h�x���`�A�[�v���̌� | |||||||||||
| |||||||||||
�F�m�Ǘ\�h�́u�U�̏K���v | |||||||||||
| |||||||||||



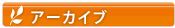

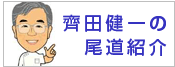

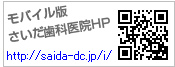

 �@�@�@
�@�@�@
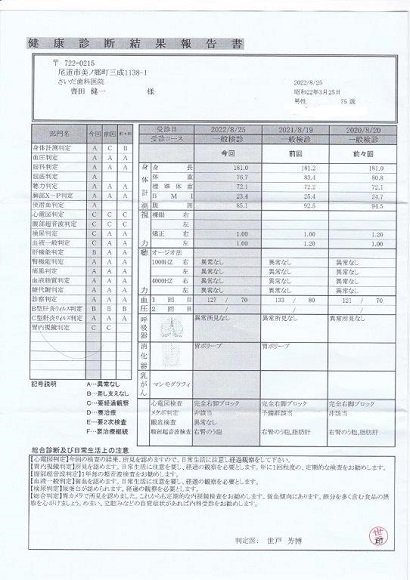
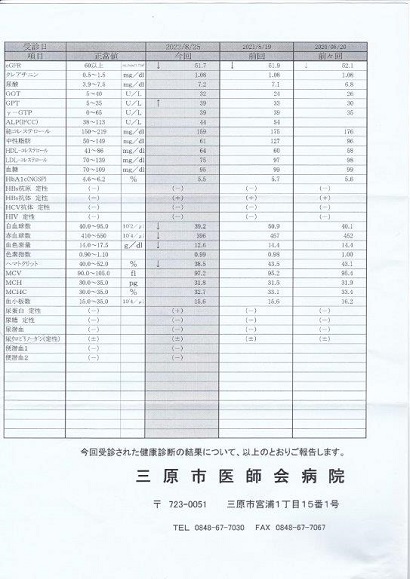
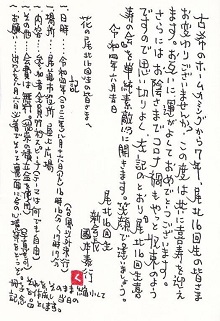 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
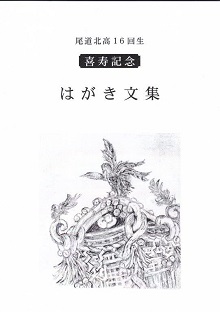 �@�@�@
�@�@�@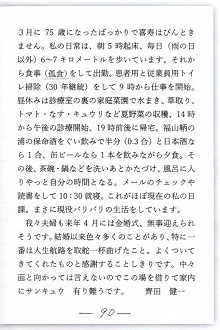
 �@�@�@
�@�@�@
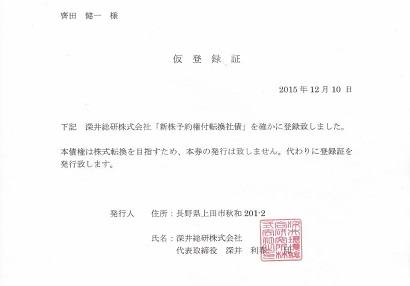
 �@�@�@
�@�@�@
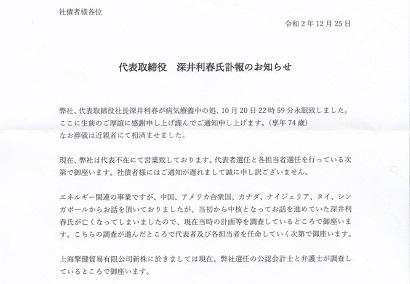
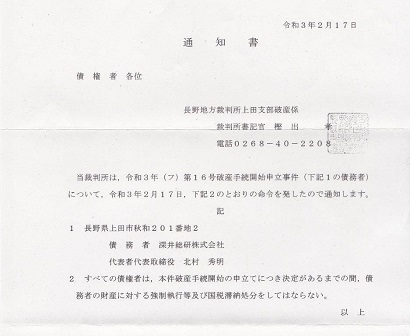
 �@�@
�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

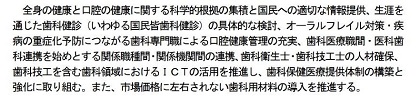
 �@�@�@
�@�@�@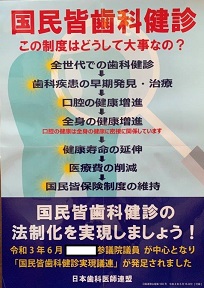
 �@�@
�@�@
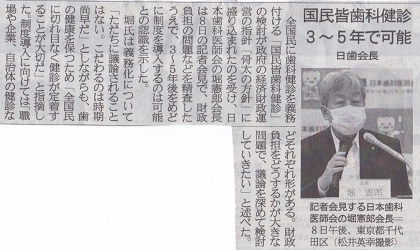
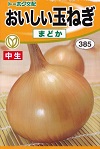 �@
�@ �@�@
�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@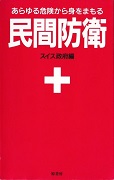
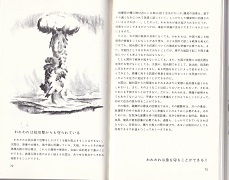 �@�@�@
�@�@�@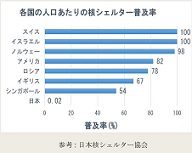
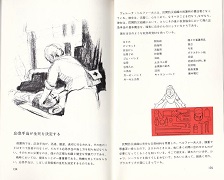 �@�@�@
�@�@�@
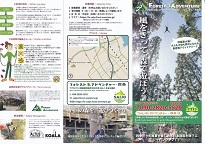 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

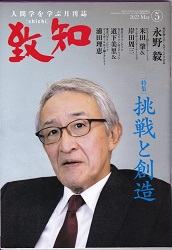 �@�@�@
�@�@�@
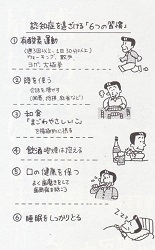 �@�@�@
�@�@�@