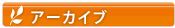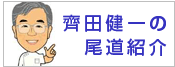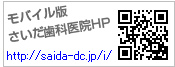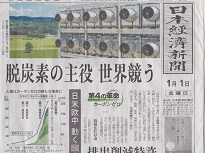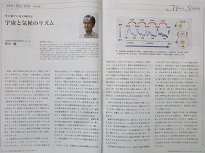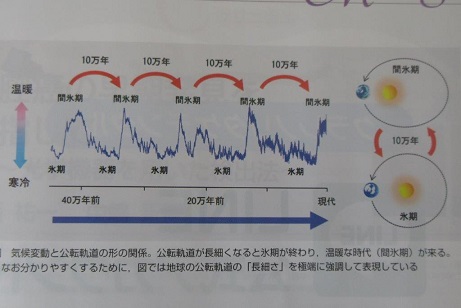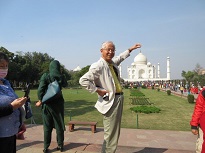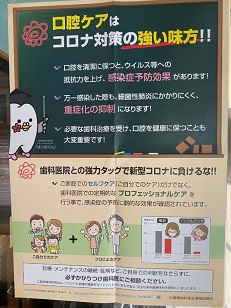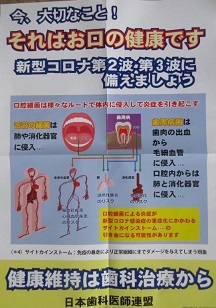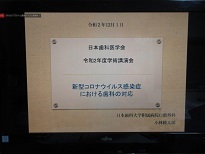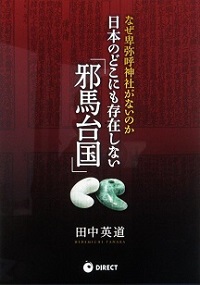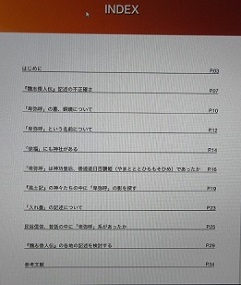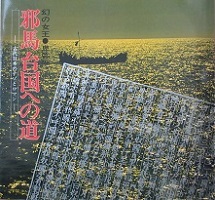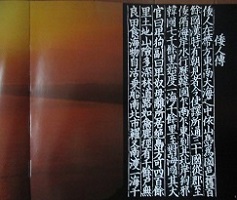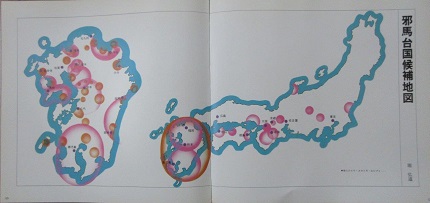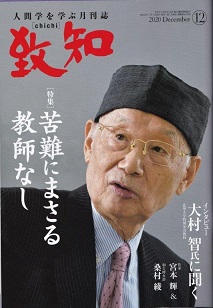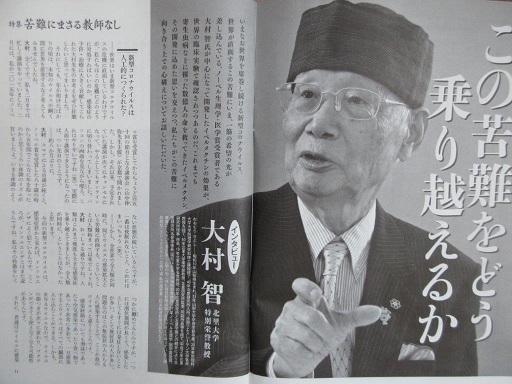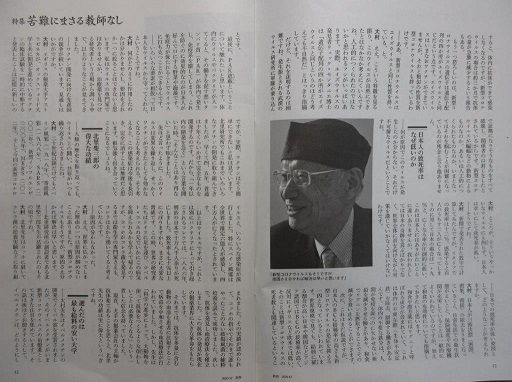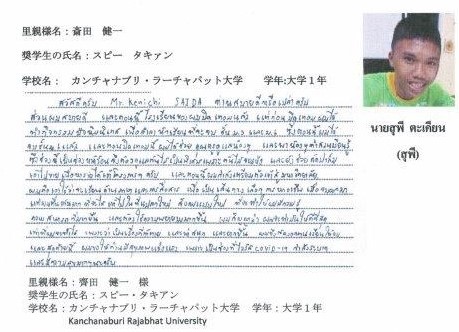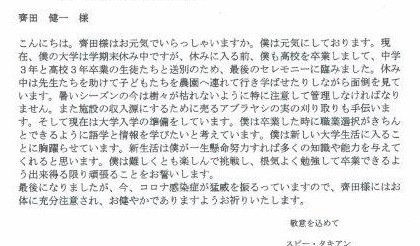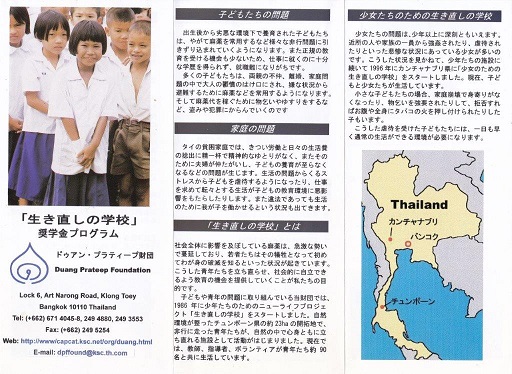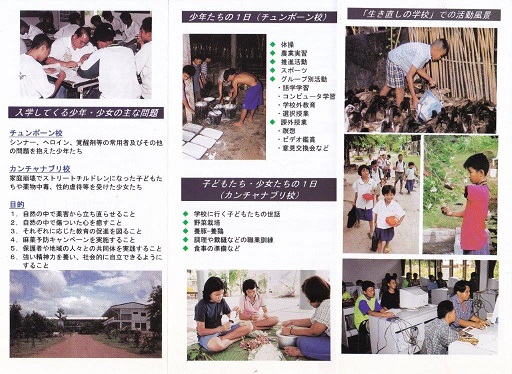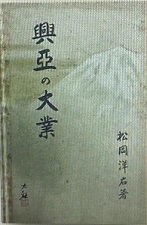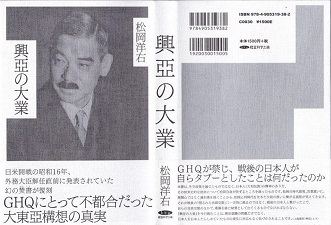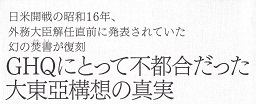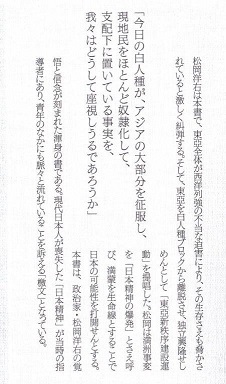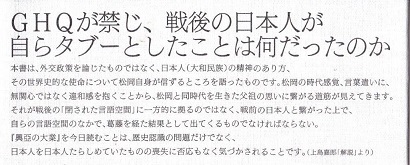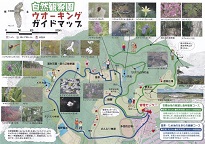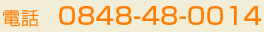患者様の声|料金表|院内販売グッズ |スタッフ紹介|スタッフ募集|アクセス|大先生(元院長)紹介|お問い合わせ|治療写真集|取り組み
大先生(元院長)のブログ
2020年を振り返って | |||||||||||
| |||||||||||
オンライン会議・オンラインセミナーに参加して | |||||||||||
| |||||||||||
邪馬台国 | |||||||||||
| |||||||||||
新型コロナウイルス(武漢ウイルス) | |||||||||||
| |||||||||||
諺「柿が赤くなれば医者が青くなる」 | |||||||||||
| |||||||||||
タイからの嬉しい知らせ | |||||||||||
| |||||||||||
今年のシルバーウイーク | |||||||||||
| |||||||||||
松岡洋右「興亜の大業」を読んで | |||||||||||
| |||||||||||
「サギソウ」初見参 | |||||||||||
| |||||||||||
« 前のページ | 院長のブログのトップ | 次のページ »