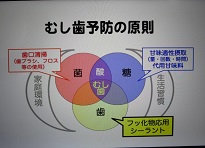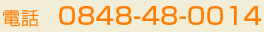���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��
��搶�i���@���j�̃u���O
���߂Ẵn���C���s�@PART �W | |||||||||||
| |||||||||||
���߂Ẵn���C���s�@PART �V | |||||||||||
| |||||||||||
���߂Ẵn���C���s�@PART�U | |||||||||||
| |||||||||||
���߂Ẵn���C���s�@PART�T | |||||||||||
| |||||||||||
�X�@�M�O���u���̍u�b�E��O���v��ǂ�� | |||||||||||
| |||||||||||
���n�̏H | |||||||||||
| |||||||||||
���������Ԃ̏d��j���[�X | |||||||||||
| |||||||||||
�厸�s�E�卪���߂�Ȃ��� | |||||||||||
| |||||||||||
���ȍu���� | |||||||||||
| |||||||||||



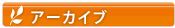

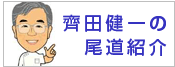

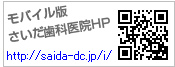

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
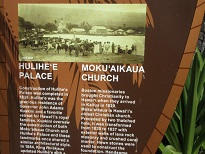 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@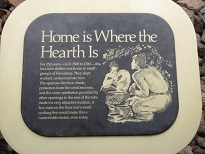
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
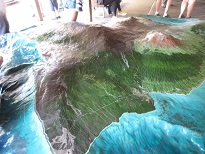 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
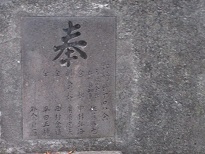 �@�@�@
�@�@�@
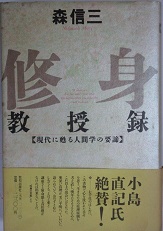 �@�@�@
�@�@�@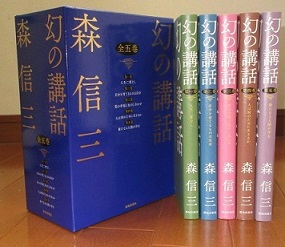
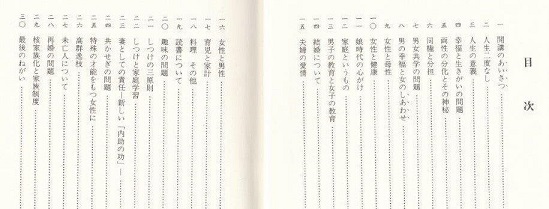
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

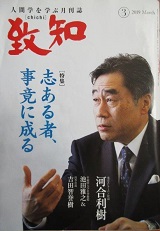 �@�@
�@�@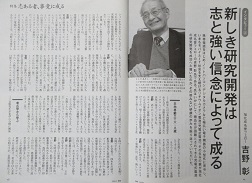
 �@�@
�@�@
 �@�@
�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
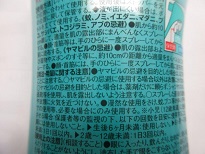 �@�@�@
�@�@�@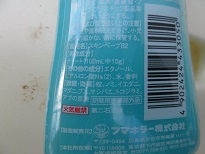
 �@�@�@
�@�@�@
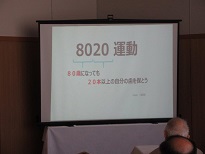 �@�@�@
�@�@�@
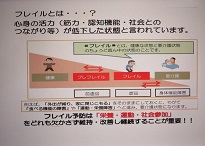 �@�@
�@�@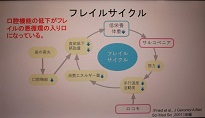
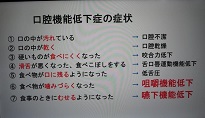 �@�@�@
�@�@�@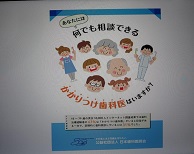
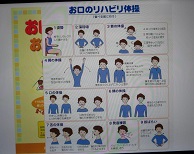 �@�@�@
�@�@�@