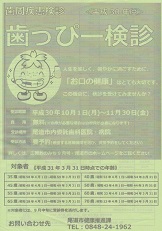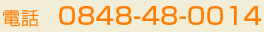���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��
��搶�i���@���j�̃u���O
�x�g�i�����s�@PART �T | |||||||||||
| |||||||||||
�������^���L | |||||||||||
| |||||||||||
ACP�ɂ��� | |||||||||||
| |||||||||||
�L���x��5���Ԏ擾�`���� | |||||||||||
| |||||||||||
�։��u�` | |||||||||||
| |||||||||||
���Ȉ�t�F�m�ǑΉ��͌��㌤�C���� | |||||||||||
| |||||||||||
�V�^�u�n����������v���� | |||||||||||
| |||||||||||
���w�{ | |||||||||||
| |||||||||||
���Ȉ�Â�������ς���I | |||||||||||
| |||||||||||



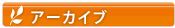

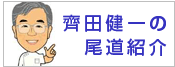

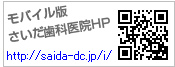

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@
�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@


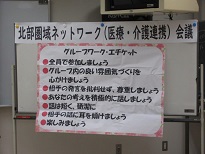 �@�@�@
�@�@�@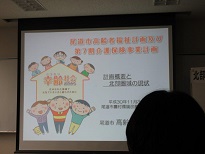
 �@�@�@
�@�@�@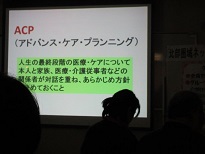
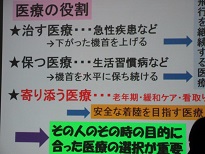 �@�@�@
�@�@�@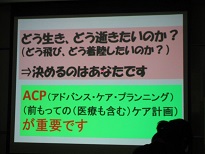
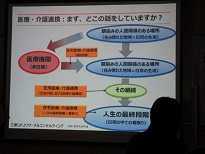 �@�@�@
�@�@�@
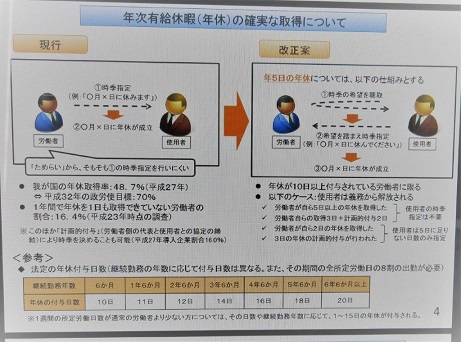
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@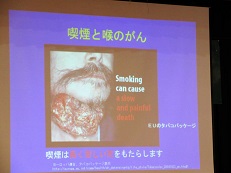
 �@�@
�@�@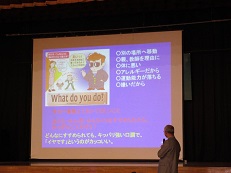
 �@�@�@
�@�@�@
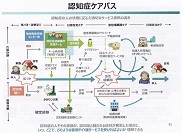 �@�@�@
�@�@�@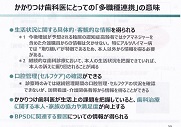
 �@�@�@
�@�@�@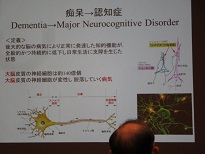
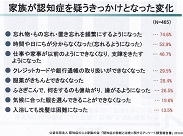 �@�@�@
�@�@�@
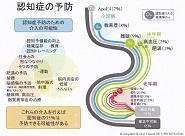 �@�@�@
�@�@�@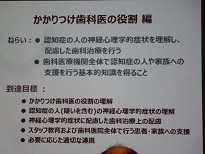
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
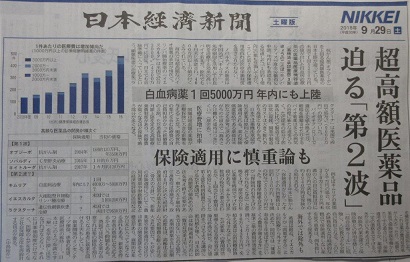

 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@
�@�@
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@
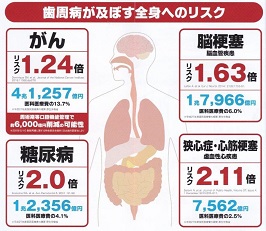 �@�@
�@�@