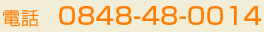���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��
��搶�i���@���j�̃u���O
���߂Ă̓����ƈ��g�x�� | |||||||||||
| |||||||||||
���N�R�x�ڂ̎D�y | |||||||||||
| |||||||||||
�͍���i���u�����̔N�\�Q�v��ǂ�� | |||||||||||
| |||||||||||
�����x�f | |||||||||||
| |||||||||||
�~�J�̐���� | |||||||||||
| |||||||||||
�u���ƌ��̌��N�T�ԁv | |||||||||||
| |||||||||||
�u�������ȁI�@�V���]�E�I�v | |||||||||||
| |||||||||||
GW�㔼 | |||||||||||
| |||||||||||
�t�̔_��ƊJ�n | |||||||||||
| |||||||||||



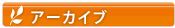

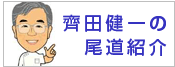

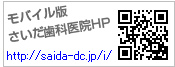

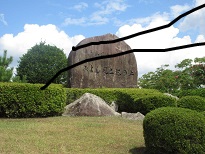 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@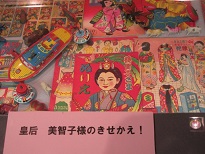
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
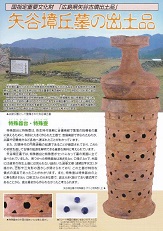 �@�@�@
�@�@�@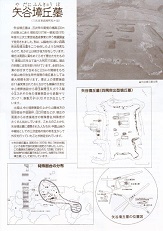
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
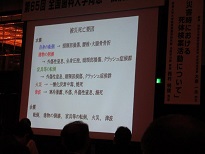 �@�@�@
�@�@�@ �@�@
�@�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�Ƃ���ŁA12���ɋA���ė��āu���{�o�ϐV���v��ǂ�ł�����A������̊ς��O��Ղ̗l�q�̋L�����ڂ��Ă����B400�N���̗��j�̂��鈢�g�x�茈���ď����邱�Ƃ̖����悤�ɑ����ė~�������̂��B
�@�Ƃ���ŁA12���ɋA���ė��āu���{�o�ϐV���v��ǂ�ł�����A������̊ς��O��Ղ̗l�q�̋L�����ڂ��Ă����B400�N���̗��j�̂��鈢�g�x�茈���ď����邱�Ƃ̖����悤�ɑ����ė~�������̂��B �@�@�@
�@�@�@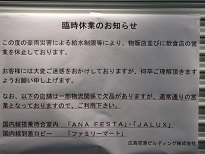
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
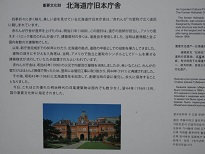 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@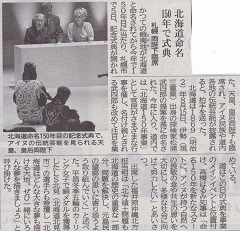
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

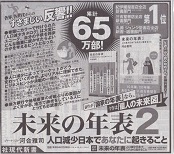 �@�@�@
�@�@�@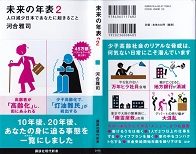
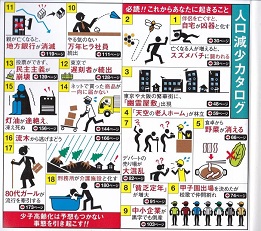
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
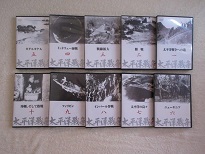 �@�@�@
�@�@�@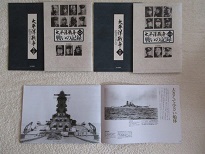
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
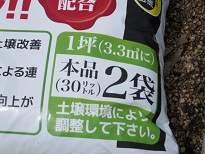 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@