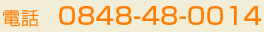���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��
��搶�i���@���j�̃u���O
���N3�x�ڂ̎D�y�o�� | |||||||||||
| |||||||||||
���q�̗����� | |||||||||||
| |||||||||||
���w���́@�u��{�����Y�v | |||||||||||
| |||||||||||
������ | |||||||||||
| |||||||||||
�䂪�q��� | |||||||||||
| |||||||||||
�D�y�o�� | |||||||||||
| |||||||||||
���߂Ẵg���R���s PART 8 | |||||||||||
| |||||||||||
���߂Ẵg���R���s�@PART 7 | |||||||||||
| |||||||||||
���߂Ẵg���R���s PART 6 | |||||||||||
| |||||||||||



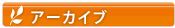

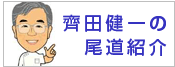

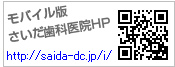

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@�@
�@�@�@�@
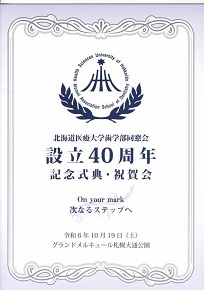 �@�@�@
�@�@�@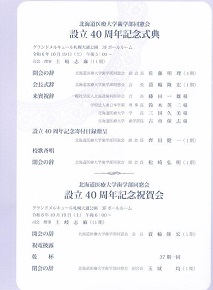 �@
�@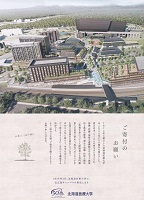 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
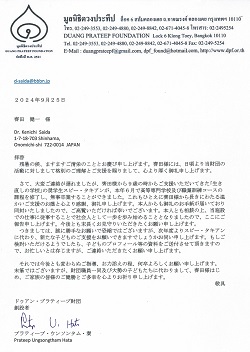
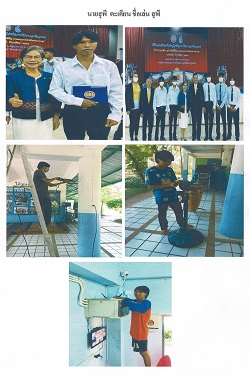
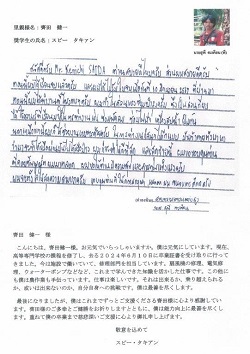
 �@�@�@
�@�@�@
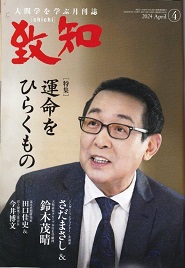 �@�@�@
�@�@�@ �@
�@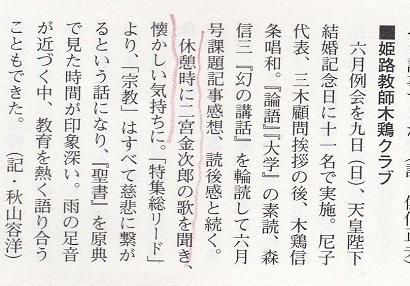
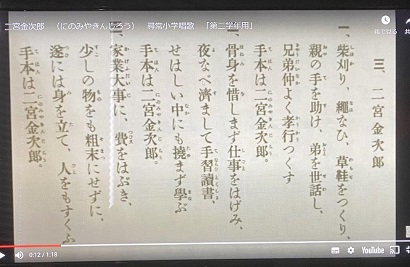
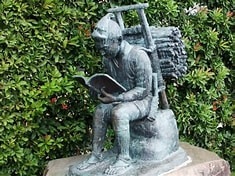
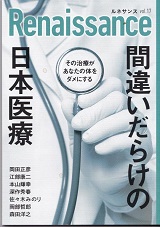 �@�@�@
�@�@�@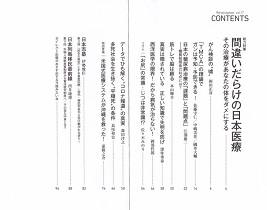
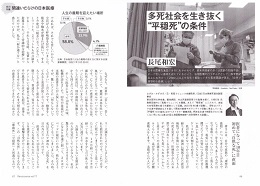 �@�@�@
�@�@�@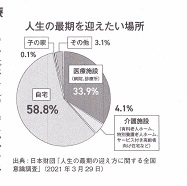
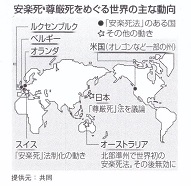 �@�@�@
�@�@�@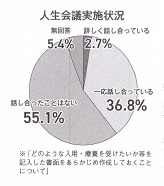
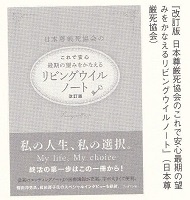
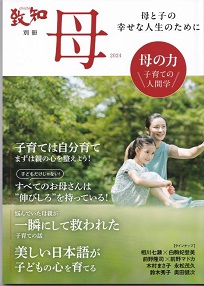 �@�@�@
�@�@�@


 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@ bb
bb �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
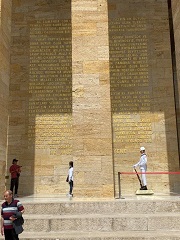 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
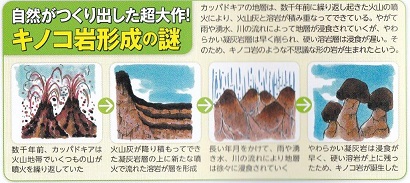
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@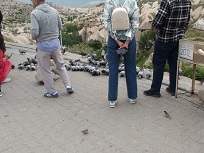 �@
�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
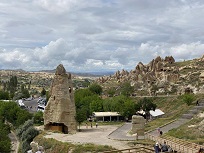 �@�@�@
�@�@�@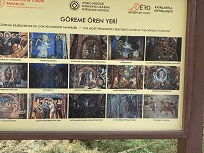
 �@�@�@
�@�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@ �@
�@ �@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
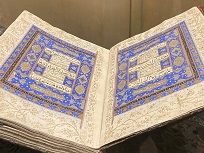 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@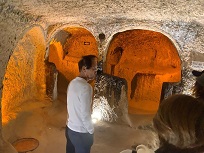
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@