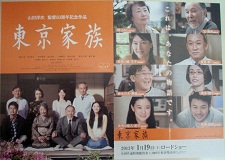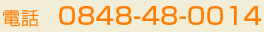���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��
��搶�i���@���j�̃u���O
���m���\�� | |||||||||||
| |||||||||||
������@PART�@�Q | |||||||||||
| |||||||||||
������@PART �P | |||||||||||
| |||||||||||
���q����̒a�����v���[���g | |||||||||||
| |||||||||||
�����Ƌ�����O�̎� | |||||||||||
| |||||||||||
�u�K���̖v�ɉԂ��炭�B | |||||||||||
| |||||||||||
�f��u��]�̍��v�Ɓu���������v���ς� | |||||||||||
| |||||||||||
�������A��o�� | |||||||||||
| |||||||||||
�f��u�����Ƒ��v���ς� | |||||||||||
| |||||||||||



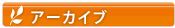

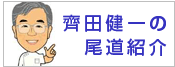

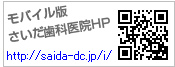

 �@
�@ �@�@
�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@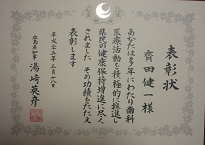
 �@�@
�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@ �@
�@ �@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@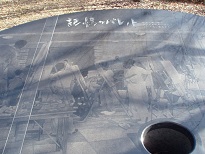 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
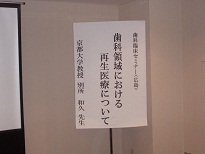 �@�@�@
�@�@�@

 �@�@
�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
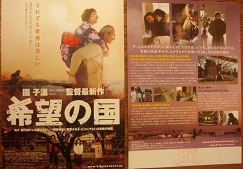
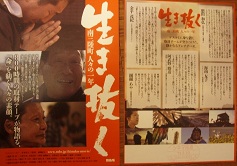
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@