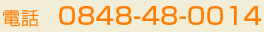��搶�i���@���j�̃u���O
��҂̌ٗp���� |
| |

| |
| | �@�����A�R���Q�O���̓��{�o�ϐV���̂P�y�[�W�ڂɁu��w�E���w�Z�i�w�҈���A�ƂT�������@���Z�ł͂R�����x�@���t�{���Z�@���{�A�U�����h�x����v�Ƃ����L�����o�����������B�܂��֘A�L���Ƃ��ĂT�ʂɂ́u����A�ƂT�������@��N�w�A�ٗp�~�X�}�b�`�@���������Ǝu���v�Ƃ������o��������B
������2010�N3���ɑ�w�⍂�Z�Ȃǂ𑲋Ƃ����N���̊w�����ΏۂŒ��r�ފw���Đ�ɎЉ�ɏo���l���܂܂�Ă���B
���q����Ƃ�������̗���ɂ����Ă��̌��o���ɏ��Ȃ��炸�V���b�N�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���e�������2010�N�t�ɑ�w�E���w�Z�𑲋Ƃ�����85���l�̂����A�����ɏA�E�����l��56��9000�l�B�����ߔN�̎�N�w�̗��E���̌X������A�E�����l�̓��A19��9000�l��3�N�ȓ��ɗ��E������Z���傫���ƕ��͂��Ă���B
�@�����đ��Ǝ��ɏA�E���Ȃ������l��A�A���o�C�g�ȂLjꎞ�I�Ȏd���ɏA�����l��14���l�B���r�ފw�Ȃǂ�����6��7000�l���܂߂�ƈ���I�Ȏd���ɏA���Ȃ������l�͑S�̂�52���@40��6000�l�ɏ��A2�l��1�l�͑�w���Ƃ����A�ƂɎ����ĂȂ��Ƃ̂��ƁB
����ɍ��Z����Љ�ɏo���l�͈�i�ƌ�������w�Ȃǂɐi�w���Ȃ�����35���l�̂����A68���ɂ�����23��9000�l������I�Ȏd���ɏA���Ȃ������B���̓�10��7000�l�����A�E�������͈ꎞ�I�Ȏd���ɏA�����B�܂�35���l�̓���2���ɂ�����7��5000�l�͏A�E���Ă��Ă�3�N�ȓ��ɂ�߂�\��������B
�@���N�i2012�N�t�j���Ƃ����w���̏A�E���藦��80.5���ʼnߋ��R�Ԗڂ̒Ⴓ�ƂȂ��Ă���B���Ԓ�����Ђɂ��ƍ��t�̑�w���҂ɑ��鋁�l�{���͑��Ƃ�0.65�{�Œ�����Ƃ�3.35�{�ł��邪���������Ɗ�]�Ƃ̎��B
�܂����݂̓��{�ɂ����鎸�Ɨ���4.9���ł��邪�A15�`24�ł�9.5���Ƃ��ׂĂ̐����ʂ��čō��ɂȂ��Ă���B���1�N�ȏ�E��������Ȃ��������Ǝ҂�1990�N�ɂ�55�Έȏ�̐�߂銄����35.7���ōł������������A2010�N�ɂ�25�`34�̔N��w��26.2%�ƑS����ōł������Ȃ��Ă���B
�@����Ƀo�u������ɔ����A�E�X�͊��Ƃ���ꂽ1993�N�ȍ~�Ɋw�Z�𑲋Ƃ���35�`44�̃t���[�^�[��2011�N���ςŖ�50���l�Ɖߋ��ō��ɂȂ����B��E�ɏA���Ȃ��܂ܔN��オ���Ă�����Ԃ������Ă���ƕĂ����B
�@�����̋L������F�X�̂��Ƃ������Ă���B���������Ă������ꏊ�������Ƃ������A�������A������Ƃɖڂ�������ΑS�����A�E�ł��邾���̃L���p�͂���悤���B
���̂Ƃ���ł͌��ݎ��ȉq���m��4�������Ă��邪�A���҂���ւ̃T�[�r�X�����}�낤�Ƃ��āA����1�l�ٗp�������ƃn���[���[�N��1�N�ȏ���o�������邪�S�������������B�����Ď��ȉq���m���w�Z�ɋ��l�[������2�N�ԏo�������Ă��邪���傪�����B
���{�ɂ͎��ȉq���m�̖Ƌ������l��22���l�ȏア�邪�A�A�Ƃ��Ă���̂�9���l���x�Ō��13���l�͏A�Ƃ��Ă��Ȃ��B���������Ȃ����Ƃł���B
�@�����Ȃ����R�͐F�X�L��Ǝv�����A�Ⴆ�Ύ������������ƈ���Đe�̐��オ������x�o�ϗ͂�����A�q�ǂ������������Ȃ��Ƃ��������e�F���Đe���{���Ƃ������Ԃ�����悤���B
�@�܂��̏�ɂ�3�N�Ƃ������t�����邪�V���L������v�Z����Ƒ�w���Ǝ҂ƍ��Z���Ǝ҂̓�27���l�ȏオ3�N�ȓ��ɗ��E����B�h���ł��Ȃ���҂�����������������B�����Ƃ�����7�N�ʼn�Ђ����߂��̂ő傫�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A��x���E����ƒ������E�҂ɂȂ肩�˂Ȃ����ꂪ����B
�@����Ɋ�Ƃ̌o�c�����������Ȃ�Β����̈����O���ɐi�o���Y�Ƃ̋����ǂ��������|���A�����ł̏A�E��������������Ȃ��Ă���B
���̂悤�Ɏ�N�J���͂����Ȃ��Ȃ�ΎЉ�ۏ�̏[���͊G�ɕ`���������ɂȂ�B�����Ő��{�̓p�[�g�̐l��������������N�������邽�߂ɉ����҂𑝂₻���Ɩ@���Ă܂ō���Ă���B����͋��炭�u�������v��������������Ȃ��B�������Β������قǍr���̒��ɂȂ肻���ŐS�z�ł���B���{���ǂ̂悤�Ȏ��ł̂������̂ł���B
| | | | 
2012�N03��20��
| |
�V�l�Ɍ��� |
| |

2012�N03��11��
| |
�����ς��f��R�{ |
| |

2012�N02��24��
| |
�V���{�u���D�卑�v��ǂ�� |
| |

| |
| | �@����A���{�o�ϐV���Ɂu���D�卑�v�Ƃ����{�̍L�����o�Ă����B���҂̓W�F�[���X�E�X�L�i�[�ł���B�ނ͐����N�w�Z�~�i�[���J�Â�����A�u�����̂X�X�e�b�v�v���̒����������Ă���B�ŋ߂͓��j���̌ߌ�ɕ��f�����u��������̂����܂Ō����Ĉψ���v�A�u�r�[�g��������TV�^�b�N���v�Ȃǂɂ��o�����Ă���A���̒��ł͗\���m���̂���l���B
�@���o�V���̍L���ɂ́u���ŁA�������𐄂��i�߂鐭�{�Ɩ�l�v�A�u�����̒����𗪒D�����s�v�E�E�E�E�ȂǁA���{��������A�����J�l�����珑�����^��
����Ɂu���Ȃ��̒��������܂�Ă���I�v�A�����܂��P�S�������̕���������Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@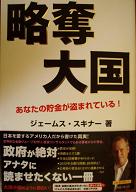
�@�ŋ߂̍���p�Ȃǂ��ςĂ��Ă�����ő��ł̘b�ȂǂŁA�Ȃ�ƂȂ����̍����s���l�܂��Ă���C�����Ă����B����ɃM���V�������s���s�Ɋׂ邩������Ȃ����̕��Ȃ���A�M���V����@�����ꃈ�[���b�p�̋��Z�s�����V�����ʂ���킵�Ă���B�Ƃ��낪���{�̍����s���̑�GDP��ł͓��{�̓M���V���������悻�Q�{���������E�ōň��ƕ��ꂽ�肵�Ă���B�����ŋ}���ł��̖{�����A��C�ɓǂB
�o�ς̎d�g�݁A�Љ�ۏ�̖��_�₩�炭�肪�����ł����B
���e�͓ǂ�ł��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���ڂ̈ꕔ���������
�E���{�l�̒��������܂�Ă���
�E���{�͂����������Ă��Ȃ�
�E�N���ƈ�Ô�S�O���J�b�g
�E ���̓l�Y�~�u�i���Ȃ������������Ă��Ȃ��Ă���s�����������Ă���A��s�ɗa�������͗a���҂ɓ����ō��ɉ����Ă���B��s�Ɍ����͖����j
�E �_�Ƃ��D�_
�E���{�ł͎�����T�X���̏���ł킳��Ă���H
�E ���{�͉����ł肪�Ȃ�
�E ���{�͎��{��`���ł͂Ȃ��Љ��`���ł���B
�E�������̒�����GDP�ɘA��������
�E���{�͔j�]�܂ł��ƂS�N�����Ȃ�
�E �Q�O�P�T�N���{�̑S��s���A�o�ϒ�~
�E ���{�̐��{�́A���łɍ��ےʉ݊���iIMF�j�ƃf�t�H���g�̎����ɂ��đ��k���Ă���
�ȂǏՌ��̓��e�ł������B
�@�����Ă��邱�Ƃ��^�����ǂ����͕�����Ȃ����A��T2���t�̒����V���́A�u��s�ő��̎O�H�����t�e�i��s�����{���̉��i�}���i�\���j�ɔ������w��@�Ǘ��v��x�����߂č�������Ƃ��킩�����v�ƕ܂����B
����͂���Ӗ����̖{�ɏ����Ă��邱�Ƃ����ۂɋN���邩������Ȃ����Ƃ���s���F�߂����Ƃ��Ƃ��v����B
�@�ŋߌl�����Y���C�O�̋�s�Ɉڂ��}�l�[�t���C�g�ƌĂ��s�����N���Ă��邱�Ƃ������悤�ɂȂ��Ă���B
�@���{�̍��ɂ́u���@�̒فv�Ȃǖ����̂ɁA������E��������ė~�����Ƃ��˂��肷�鍑���̑��ɂ���肪����Ǝv���A��͂�l�͎����w�͂����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����B
�@���̖{�͂���l�ɂƂ��Ă͎����ł�������A����l�Ɏ���Ă͖ڂ��炤�낱��������Ȃ��B
�o����Γǂ܂�Č��Ă͂������ł��傤���H
| | | | 
2012�N02��12��
| |
�f��u�G���f�B���O�m�[�g�v���ς� |
| |

2012�N02��05��
| |
�w�`�ϐ� |
| |

2012�N01��26��
| |
�ŋߊς��f�� |
| |

2012�N01��19��
| |
�����x�� |
| |

2012�N01��09��
| |
50�N�ڂ̓����� |
| |

2012�N01��04��
| |
« �O�̃y�[�W �b
�@���̃u���O�̃g�b�v
| ���̃y�[�W »



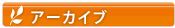

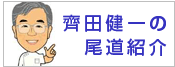

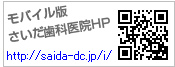


 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
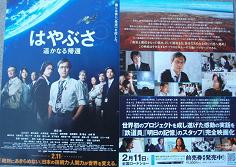 �@�@�@�@
�@�@�@�@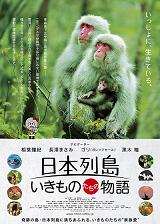
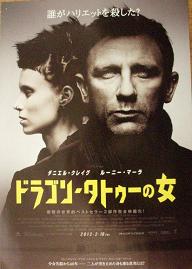 �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@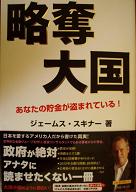
 �@�@
�@�@
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@
�@ 
 �@
�@
 �@
�@
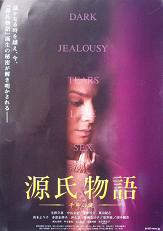
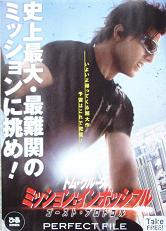 �@�@�@
�@�@�@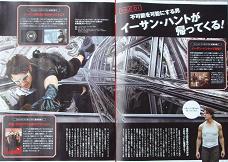

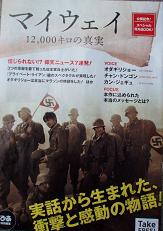 �@�@�@
�@�@�@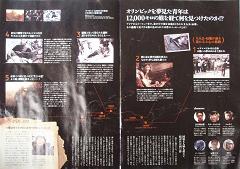

 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@